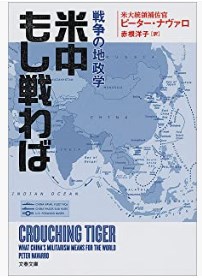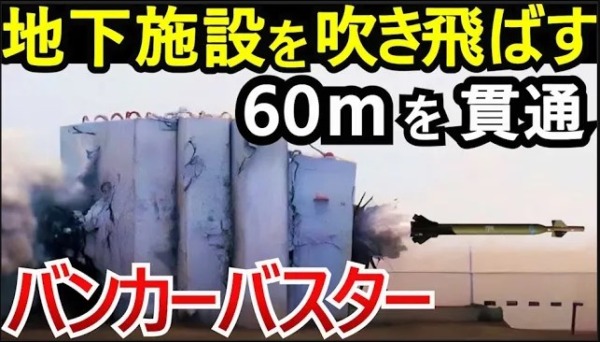Amazonのオーディオブック12万タイトルの本を好きなだけお楽しみいただけます。・本の1冊分の月額で聴き放題
・料金をメリットが上回る
・いつでも読書できる
・読書量が格段に増え、積読が解消される
・長時間の読書も目が疲れない
・聴くたびに学びを感じる
無人機、一般にドローンと呼ばれるこれらの機体は、もともと軍事目的で開発がスタートしたものだが、今では日常生活のさまざまな場面で利用されるようになった。
しかしながら、ウクライナのような戦場では、ドローンは再びその原点に戻り、「戦争の道具」としての一面を強く見せつけている。
風に乗るプロペラの音、それは平和な日常とはかけ離れた、生と死が交錯する戦場の現実を象徴する音でもある。
今回は、戦争のルールと在り方を変えたドローンと米空軍のAI戦闘機部隊、そして自衛隊が遅れをとる理由について解説していこう。
この記事に書かれている内容は
ドローン技術が変えた戦争のルール 「貧者の武器」から「戦略的必需品」へ

ドローンの戦争利用は、その可能性とリスクの両方を浮き彫りにしている。
例えば、2020年のナゴルノ・カラバフ紛争では、ドローン技術が戦場での優位を決定づける要因の一つとなり、世界中の軍事関係者の関心を集めた。

アゼルバイジャンがAI技術を搭載したドローンを駆使してアルメニアに勝利し、30年にわたる対立の中で失われた領土の一部を取り戻すという快挙を成し遂げたことは、世界中の軍事関係者に衝撃を与えた。
この勝利は、戦場での戦術と技術の革新がいかに重要かを示す典型例である。
これらのAI搭載ドローンは、従来の偵察技術では見つけ出せなかった、壕に潜む兵士や装甲車両を発見し、攻撃する能力を持っていた。
兵士が持つ電子機器の信号を検知することで、隠れている敵の位置を特定し、精密な攻撃を実行することが可能になった。

この技術により、アルメニア軍は突然の攻撃に晒され、大きな混乱に陥った。
アゼルバイジャンがこのように先進的な兵器を用いることができた背景には、同国と親密な関係にあるトルコからの技術提供があったからだ。
軍事力や科学技術の面で目立った存在ではないアゼルバイジャンが、AIドローンという最新鋭の武器を戦場で効果的に活用し、地政学的に重要な勝利を収めたことは、世界の戦争の歴史に新たなページを加えたと言えるだろう。
この紛争は、ドローンが「大国だけの武器」ではなく、「誰もが使える時代」へと移行したことを示す象徴的な事件となった。

アゼルバイジャンの成功は、ドローンが「貧者の武器」としても機能することを証明し、多くの国々が低コストで効率的な武器システムとしてドローンを見直すきっかけとなった。
現代の戦場では、ドローンによる偵察、監視、さらには攻撃が一般的な戦術として取り入れられ、ゲームチェンジャーとして戦争の様相を根本から変えている。
この進化は、技術がどのようにして戦争のルールを書き換えうるかを示す鮮明な例であり、戦略的変化をもたらすかを示している。
ドローンがもたらす可能性とは裏腹に、その乱用によるリスクや倫理的な課題もまた、現代社会が直面している重要な問題である。
無人機vs有人戦闘機 驚異のコストパフォーマンス

アメリカ軍が運用するドローンの「MQ-9 リーパー」は無人機の中で最も高い攻撃能力を持っており、その機体価格は1機あたり約1700万ドルだ。

一方、リーパーのベースとなった「プレデター」は更に低コストの450万ドルとされている。

これに対し、ステルス性を備えたF-22戦闘機の1機あたりの価格は約3億5000万ドルと高額である。
この金額であれば、リーパーを20機、プレデターを77機購入することが可能であり、F-22を1機運用する資金で、複数の無人機を運用することができる計算になる。
「リーパー」の戦闘行動半径はF-16戦闘機の6倍にも及び、長時間の飛行が可能であることが大きな利点とされている。
パイロットの疲労を考慮する必要がなく、燃料が許す限り数十時間にわたって飛行し続けることができるため、長期間の監視や偵察任務に非常に適している。
この持久力は、有人戦闘機では実現困難な任務を可能にする。
このような無人機の特性は、現代戦の多様な要求に応える柔軟な運用が可能であることを示しており、低コストでありながらも高い戦闘能力と持続性を提供する。
無人機は、有人戦闘機と比較しても、特定の任務においては優れた選択肢となり得る。
これらの点から、「リーパー」や「プレデター」は、コストと効率性を重視する軍事戦略において重要な役割を果たしている。
アフガニスタンやパキスタンでの対テロ作戦に投入される無人機は、離着陸の際には現地の飛行場で操作されるが、その他の時間はアメリカ本土の基地から通信衛星を通じて遠隔で操縦される。
これにより、オペレーターは物理的に戦場から離れた場所にいながら、地球の反対側で無人機を操作し、ミサイルの発射や爆弾の投下を行う。
戦場での指揮官も無人機が捉えた映像や情報をリアルタイムで監視し、攻撃の決定に関わることがある。
しかし、実際に攻撃のボタンを押すのはアメリカ本土の基地にいるオペレーターだ。
彼らはまるで一般職員のように基地に通勤してシフト勤務をこなし、勤務時間終了後は家路につく。
初期の頃、これらのオペレーターは戦闘機パイロットなどの経験者から選ばれていたが、需要の増大に伴い、実戦や飛行経験が一切ない者が無人機を操ることも珍しくなくなった。
このような遠隔操作による戦闘は、戦争のあり方を根底から変えている。

オペレーターは物理的には安全な場所にいるが、戦争の最前線で重大な決断を下し、人命に関わる操作を行っている。
モニターを見ながら、コントローラーを使用して、まるでテレビゲームのようにミサイルを発射して敵を攻撃する。
この状況は、現代戦における人間の役割と戦争の倫理について、我々に多くの問いを投げかける。
遠隔操作が可能にする戦争の新たな形は、その参加者にどのような心理的影響を与え、また、これが戦争の未来にどのような影響をもたらすのだろうか?
そんな中、アメリカ空軍は、空対空戦闘における新たな戦術を切り開く計画を進行中である。

この野心的な計画では、F-16 をベースに自律飛行ソフトウェアを搭載した試験的なプログラムが展開される。
その目的は、有人戦闘機と共に作戦を行う無人戦闘機を開発することにある。
2024年度には、そのための予算として5000万ドル(約69億円)が割り当てられている。
これらの無人機は、次世代戦闘機やF-35Aといった有人機と共に行動し、1機の有人機に対して2機の自立機体が配備される計画である。
これは、ミサイルなどの兵装を搭載し、敵に対して妨害などの電子戦能力も備える。
さらに、他の航空機の前方を飛行し、最新のレーダーや電子警告システムなどのセンシング機能を用いて、情報収集、監視、偵察任務を行う。
計画によれば、6機のF-16が改造され、将来的には少なくとも1000機の機体を配備する意向があるという。
今後5年間で合計約1億2千万ドル(約165億円)が投じられる予定だ。

この自律型航空機の開発は、空対空戦闘のパラダイムを変える可能性を秘めており、有人戦闘機と無人戦闘機が共に作戦を遂行する新時代の幕開けを告げている。
これは、日本が2035年に配備をめざし開発している「第6世代戦闘機F-3」とおなじ構想であり、無人機が有人の戦闘機と連携するというものである。
このような技術革新は、将来の空中戦の概念を再定義すると同時に、戦術的な柔軟性と戦闘能力を大幅に向上させることが期待される。
「今すぐ必要!!」自衛隊が求める ドローンの現状と開発停滞の原因

日本は、現時点で航空自衛隊の空撮用ドローンのみを運用しており、攻撃可能なドローンは持っていない。
アゼルバイジャンとアルメニアが衝突した際に、ドローンにより防空能力を無効化し地域を奪還したことで、その必要性が浮き彫りにされた。
ただし、防衛省がドローン開発をしていなかったわけではない。
当時、富士重工業と共同で研究開発プロジェクトを実施し、技術的には成功を収めたが、需要が見込めずプロジェクトは終了した。
これは、技術は身につけたが、陸海空自衛隊からの具体的な要望がなく、開発を進める動機が失われたことを意味する。
わずか数年前まで、自衛隊はドローンへの需要を否定していたが、予算の制約がその理由だった。
しかし現在、陸上自衛隊の師団長は「数百機のドローンがすぐにでも必要」と強く求めている。
防衛省が一般企業だったら、下請法で問題視されるような状況にある。

防衛関連の企業への資金流通も不足しており、これまでの研究開発費は1000億円程度で推移していた。
防衛省と契約を結ぶ主な企業は大企業かもしれないが、防衛部門は社内での優先度が低く、資金確保が困難である。
装備の必要性が明らかになっても、即座に対応することは難しく、運用可能になるまで「10年かかる」とされる。
もちろん自衛隊はそんなに待てず、結果として米国から購入することになるが、これが続くと国内の防衛産業への影響が大きく、悪循環に陥る。
このジレンマは見過ごせないほど重要な問題だ。
自衛隊の将来を考える上で、どのような対策が考えられるだろうか?
日本のドローン技術とその軍事利用に関する現状は、世界の急速な発展の流れと比べて、著しく遅れを取っている。

一方、中国は近年ドローンを日本海や東シナ海まで飛行させ、偵察や試験飛行を行っており、航空自衛隊がスクランブル発進をしている。
無人機に対して有人機を向かせる時点で、日本は遅れをとっているといえる。
もし有事の際にこのような状況で攻撃されれば、パイロットと機体を失うことになる。
日本のドローン関連予算は限定的であり、その活用は実戦的な運用にはまだ程遠い状態にある。
2004年に陸上自衛隊に導入された遠隔操縦観測システムやその後の改良型、輸入された偵察用ドローンなど、日本が導入したドローンは、主に偵察や情報収集に限られており、攻撃型ドローンの導入計画は現在も存在しない。

岸田首相の「攻撃を実施できる無人化された装備品の取得について具体的な計画はない」という声明は、日本がドローン技術の軍事利用に対して慎重な姿勢をとっていることを示している。
一方で、自衛隊のドローン活用の遅れは、国際社会での情報収集能力や戦術的な柔軟性において、日本が不利な立場にあることを意味している。
自衛隊内でもドローンの重要性を理解している人物がいるにも関わらず、組織的な導入に至らなかった背景には、ドローンに対する認識の問題があったことを示唆している。
自衛隊が組織としてドローン技術を導入し、その運用に本格的に取り組むには、ドローンの概念を再定義し、その有効性を組織全体で共有することが必要である。
次の動画では、ウクライナが使用した迫撃砲ドローンとダンボール製ドローンについて解説しよう。
Amazonのオーディオブック12万タイトルの本を好きなだけお楽しみいただけます。・本の1冊分の月額で聴き放題
・料金をメリットが上回る
・いつでも読書できる
・読書量が格段に増え、積読が解消される
・長時間の読書も目が疲れない
・聴くたびに学びを感じる