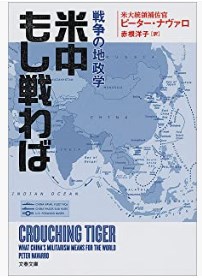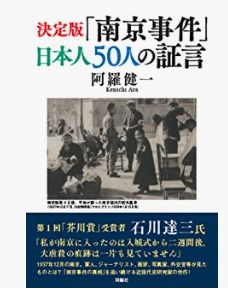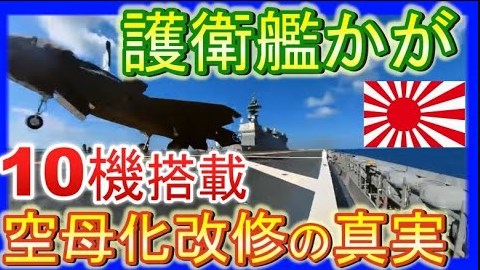Amazonのオーディオブック12万タイトルの本を好きなだけお楽しみいただけます。・本の1冊分の月額で聴き放題
・料金をメリットが上回る
・いつでも読書できる
・読書量が格段に増え、積読が解消される
・長時間の読書も目が疲れない
・聴くたびに学びを感じる

時速200kmで進む戦闘機が、わずか2秒で完全停止する技術
現代の空母といえば、その特徴的な斜めの飛行甲板が目を引く。 この一見奇妙な設計には、実は航空機運用の歴史に裏打ちされた重要な理由がある。 戦闘機を運用する通常の航空基地では、3000m級の滑走路が当たり前だ。 しかし、海上の限られたスペースしかない空母では、発艦に使える距離はわずか約80m、着艦には約90mしかない。 これは陸上基地の滑走路のおよそ30分の1という過酷な条件である。
この制限された空間で、いかにして戦闘機を安全に発着艦させるか。 その答えが「アングルドデッキ」という斜めの甲板だった。 なぜ空母には斜めの滑走路が必要なのか。 その開発秘話から最新鋭空母の技術まで、空母進化の核心に迫っていこう。
この記事に書かれている内容は
第1章:軍艦から航空機を飛ばす壮大な挑戦
「飛行甲板」という革命的発想
世界で初めて軍艦から航空機を飛ばそうと計画したのは、常に革新的なアイデアが生まれるイギリス海軍であった。 第一次世界大戦中の1917年、軽巡洋艦「フューリアス」に対して行われた大胆な改修が、空母の歴史の始まりである。 艦首甲板上の前部砲塔を撤去し、長さ70m、幅15mの飛行甲板を取り付けるという当時としては画期的な試みだった。
しかし、この初期の設計には致命的な欠陥があった。 発艦はできても着艦は事実上不可能だったのである。 速度の遅かった当時の航空機でさえ、70m程度しかない飛行甲板に安全に着艦するのは至難の業だった。 艦載機が衝突しないようにネットを張る方法も考案されたが、実戦では使い物にならなかった。
「フューリアス」の失敗から学んだイギリス海軍は、第一次世界大戦直後、商船を改造して空母アーガスという新たな空母を開発する。 この空母には飛行甲板上に構造物を設けない「全通甲板」が初めて導入された。 これが世界初の実用的な空母と評価されている。
「日本海軍の挑戦」- 初の専用設計空母
イギリスの空母開発に大きく影響を受けたのが旧日本海軍だった。 日本海軍は世界に先駆けて「鳳翔」という、改修ではなく最初から空母として設計・建造された艦を就役させた。 煙突や艦橋と全通甲板を両立させるため考案された「アイランド型」の配置は画期的であり、全通甲板を備えていた。
しかし、鳳翔もやはり発艦と着艦を同時に行うことができないという根本的な問題を抱えていた。 鳳翔は甲板上に縦方向のワイヤーを張り、航空機は斜め方向から甲板上に進入してフックをワイヤーに引っかけて制動する「縦索方式」を採用した。 これは現代の空母の着艦システムの原型となる重要な技術革新だったのである。
日本海軍はその後、ワシントン海軍軍縮条約の影響で戦艦としての建造が中止になっていた「赤城」と「加賀」を空母に転用し、多段飛行甲板を持つ独自の設計を採用した。 この多段甲板の発想は、限られたスペースで効率的に航空機を運用しようとする工夫の一つだったが、結果的に複雑な運用を強いられることになった。
結局、第二次世界大戦中の空母は、発艦作業と着艦作業にそれぞれ専念する時間を設けることになる。 しかしこの方式には大きな弱点があった。 着艦時にオーバーランなどの事故が生じた場合、前方に駐機している機体に衝突し、飛行甲板全体が使用不能になる危険性が常に付きまとっていたのだ。
第二次世界大戦後、ジェット機の登場により状況は一変する。 高速で着艦するジェット機は、オーバーラン事故の可能性がさらに高まり、新たな解決策が求められていた。 そこで再び空母発祥の地イギリスから、革命的なアイデアが生まれることになる。
第2章:アングルドデッキの誕生 – 空母の進化の決定的瞬間
「斜め甲板」という革命的発想
戦後、ジェット機の時代を迎え、空母の設計は根本的な変革を迫られていた。 1950年、イギリス海軍のデニス・キャンベル大佐が後部に角度をつけた甲板を取り付け、発着艦を分離できないかと考案した。 この斬新なアイデアは、空母運用の歴史を変える革命的な発想だった。
もし直線甲板のままだと、着艦に失敗した機体は前方に駐機している航空機に衝突する危険がある。しかし斜め甲板ならば、着艦に失敗しても機体はそのまま上昇して再着艦に挑むことができると当時の設計者は考えた。
このアイデアは1952年、イギリス海軍のコロッサス級空母「トライアンフ」で初めて試験的に採用された。 その後、アメリカ海軍のエセックス級空母「アンティータム」にも採用され、本格的な運用が開始された。 実験の結果は驚くべきものだった。 着艦の失敗率が大幅に減少し、航空機の運用効率が飛躍的に向上したのである。
時速200kmから2秒で停止する驚異の技術
現代の空母では、アングルドデッキと呼ばれる斜め甲板を備えているのが標準となっている。 これにより、空母の飛行甲板では発艦作業中であっても艦載機の着艦収容が可能になり、発艦と着艦を同時並行で行えるようになった。
多くの人は空母の滑走路が2本あると思っているが、実際には3本ある。 空母前方にある2本はカタパルトを装備した「発艦専用」で、斜め甲板は正確には「離着艦用」である。 斜め甲板にもカタパルトがあり、こちらからも発艦が可能だ。
発艦専用デッキと離着艦用デッキを分けることで、着艦させながら発艦させることができ、効率よく艦載機を展開できる。 また、事故の被害を最小限に抑えるという重要な目的もある。
空母に帰還する戦闘機は、わずか100mほどの距離で完全に停止しなければならない。 そこで使われるのが、飛行甲板に張られた4本のアレスティングワイヤーである。 艦載機が備える着艦フックをこのワイヤーに引っ掛けることで、内部機構がゆっくり制動し、急停止させるという仕組みだ。
着艦速度は、接近時には時速550〜650km、着艦直前でも時速200kmという猛スピードである。 この状態から、わずか2秒で完全停止させるという驚異的な技術が実現されている。
空母への着艦はコントロールされた墜落と言われるほど難しいとベテランパイロットは語る。 広大な海に浮かぶ空母も、パイロットの視点からは「切手のように狭いところ」に映るという。 着艦が失敗した場合、着艦フックをワイヤーに引っ掛けてから4秒以内に止まらないと海に落下してしまうという緊張感の中での操縦である。
海が荒れていれば空母は上下左右に動揺し、日照のない夜間の着艦はさらに困難を極める。 ベテランパイロットでさえ、毎回緊張を強いられる極限の任務なのだ。
アングルドデッキの最大の利点は、着艦に失敗しても待機中の航空機に追突する危険がないことである。 直線甲板でも、着艦専用の滑走路を斜めにすれば、失敗してもフルパワーでそのまま離艦し、再度着艦にチャレンジすることが可能になる。 万一失敗しても被害を当該機だけに限定できるという大きなメリットがあるのだ。
こうして、アングルドデッキは空母運用の安全性と効率性を劇的に向上させる革命的技術として確立された。 しかし、すべての空母がこの設計を採用しているわけではない。 現代の日本の護衛艦「いずも」と「かが」は、なぜアングルドデッキの改修を行わないのだろうか?
第3章:次世代空母の姿 – 垂直離着陸機が変える未来
「垂直着陸の革命」 F-35Bがもたらす変化
海上自衛隊が空母化を進めている護衛艦「いずも」と「かが」は、アングルドデッキの改修を行わない計画だ。 なぜなら、これらの艦に搭載予定のF-35B戦闘機は、短距離離陸・垂直着陸が可能な特殊な戦闘機だからである。
F-35Bとアメリカの空母で運用されるF-35Cの大きな違いは、離着陸の方式にある。 F-35Bは、エンジンノズルが下を向き、コックピット後方のリフトファンが下向きの力を噴射することで、空中でホバリング(空中停止)して、そのまま垂直に着艦することができる。 燃料や武器を減らせば垂直離陸も可能だが、通常は短い距離で加速しながらエンジンノズルの方向を変え、翼の揚力も利用して離陸する。
この特性により、米空母のような強制的に加速させるカタパルトや、アングルドデッキといった複雑な設備が不要になるのだ。
垂直着陸機能により、F-35Bは従来の戦闘機と比べて格段に柔軟な運用が可能になると防衛専門家は評価する。 限られたスペースしかない艦上でも効率的な運用ができ、緊急時の対応能力も高いという特長がある。
「進化する空母技術」日本型空母の現実
日本がF-35Bを運用するため「いずも型護衛艦」に施す改造は、主に飛行甲板の耐熱強化である。 F-35Bのジェットエンジンが下向きに排出する高温の排気に耐えられるよう、特殊な処理が必要になった。
飛行甲板には「ノンスキッド」と呼ばれる滑り止め塗装が施されている。 これは単なる滑り止めではなく、エンジン排気、燃料油、酸、アルカリ、塩水などに対して強い耐久性を持つ特殊な塗料だ。 通常のノンスキッドは982度までの高温に耐えられるが、F-35Bのエンジン排気を直接浴びる箇所にはさらに耐久性の高い特殊なノンスキッドが使用されている。
一方で、アメリカの最新鋭空母「ジェラルド・R・フォード級」との規模の差は歴然としている。 いずも型護衛艦の基準排水量は2万トン程度で全長は250mだが、フォード級空母は基準排水量約10万トンで全長は337mもある。 この規模の違いは、運用できる航空機の数と種類に大きく影響する。
「いずも型をアングルドデッキに改修するのは現実的ではない」と海軍建築家は指摘する。 後から大規模な改修を行えば、重心や重量バランスが崩れるリスクがある。 さらに、仮に船体の改造が完了しても、船体サイズから搭載できる艦載機が少なすぎて、本格的な運用ができず非効率的になる可能性が高い。
それでもF-35Bの運用能力は、日本の防衛力に新たな次元をもたらす。 限られたスペースで最大限の効果を発揮できるよう、日本独自の運用方法が模索されている。
垂直着陸機能を持つF-35Bと従来型の空母運用は、それぞれ一長一短がある。 世界の海軍は今後も状況に応じて最適な組み合わせを追求していくだろう。 空母の進化は、アングルドデッキという革新的技術によって大きく飛躍したが、垂直離着陸機の登場により、さらなる変革期を迎えているのだ。
空母の甲板に斜めの滑走路を設ける「アングルドデッキ」は、空母運用の安全性と効率性を劇的に向上させた革命的技術である。 第一次世界大戦から始まった空母開発の歴史は、常に限られた艦上スペースでいかに効率的に航空機を運用するかという課題との闘いだった。
イギリス海軍から始まり、日本やアメリカに引き継がれた空母技術は、第二次世界大戦後のジェット機の登場により新たな局面を迎える。 斜めの甲板という一見奇妙な設計が、着艦失敗時の安全性確保と、発着艦の同時並行運用という二つの重要な課題を見事に解決したのである。
現代では、F-35Bのような垂直離着陸機能を持つ戦闘機の登場により、空母設計の選択肢が広がっている。 日本の「いずも」と「かが」は、アングルドデッキではなく垂直着陸機能を活かした設計を選択した。
時代とともに進化する空母技術は、海洋国家の安全保障における重要な要素であり続けるだろう。 斜めの滑走路という革新的発想が、海の戦場に新たな次元をもたらしたのである。
Amazonのオーディオブック12万タイトルの本を好きなだけお楽しみいただけます。・本の1冊分の月額で聴き放題
・料金をメリットが上回る
・いつでも読書できる
・読書量が格段に増え、積読が解消される
・長時間の読書も目が疲れない
・聴くたびに学びを感じる