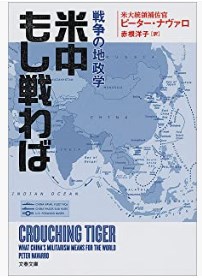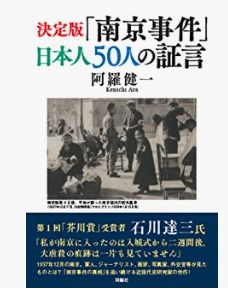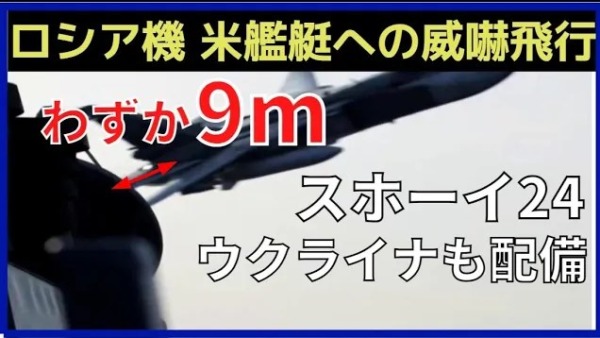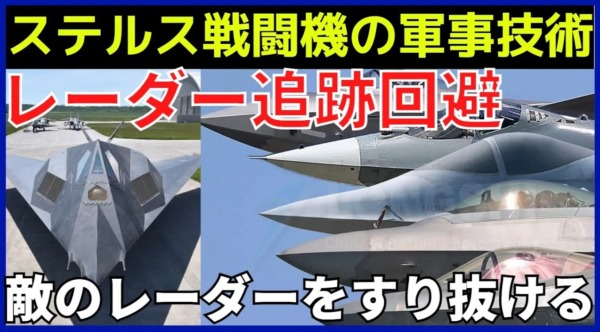Amazonのオーディオブック12万タイトルの本を好きなだけお楽しみいただけます。・本の1冊分の月額で聴き放題
・料金をメリットが上回る
・いつでも読書できる
・読書量が格段に増え、積読が解消される
・長時間の読書も目が疲れない
・聴くたびに学びを感じる
護衛艦が洋上で活動を続けるには燃料や水、食糧、さらには弾薬といった重要な物資を常に補給する必要がある。
これらを毎回港に戻って補給していたのでは、作戦の効率が著しく損なわれる。
そのため、補給艦が護衛艦に随伴し、まるで海を行く移動型ガスステーションのように活躍するのである。
一方、戦闘機も空中で燃料を補給するという神業のような技術がある。
今回は、部隊が前線で任務を継続するために必須の洋上補給と空中給油の驚きに方法について解説していこう。
洋上給油の驚異の技術!30mの間隔で行う燃料補給の技術とは?
洋上給油とは、航海中の艦船間で燃料を移送する方法で、補給艦と艦艇が約30~50メートルの間隔を保ちつつ同じ針路速力で航行する極めて高度な技術を要するものだ。
この作業では、まず初めに補給艦が専用の装置を使用してワイヤーを発射し、受け取った艦艇はそれを接続する。
次にワイヤーに沿って蛇管と呼ばれるホースが送られ、艦艇の給油口に接続する。
この状態を維持しながら長いときは数時間にわたって燃料が供給される。
補給艦の主任務は、護衛艦をはじめとする艦艇部隊への燃料供給であるが、長い航海になると食糧や消耗品などの物資の補給も必要となってくる。
その場合は「ハイライン」と呼ばれる装置を使用して食糧や物資を供給する。
また、人員を「カゴ」に乗せて移動させることも可能である。
見た目はまるでアトラクションのように見えるが、落下したら海に飲み込まれるため非常に危険が伴う作業である。
両艦はこの間、距離と速度を正確に保持しながら並行して進む必要があり、これには操艦技術のみならず、隊員の練度と忍耐も求められる。
このプロセスを、自動車で例えるなら1メートル未満の距離を数時間保ちながら走行しつつ、隣の車に荷物を渡すようなもので、隊員たちの厳しい訓練とチームワークの結晶である。

海自の2種類の補給艦 現在、海上自衛隊は基準排水量8100トンの「とわだ」型補給艦3隻と、1万3500トンの「ましゅう」型補給艦2隻、合わせて5隻の補給艦を運用している。

この「ましゅう」型は、「とわだ」型の改良型であり、約5000トンの大型化が図られている。
このサイズアップにより、燃料や各種補給物品の搭載能力が大幅に向上しており、「とわだ」型の1.5倍の燃料と2倍以上の水を積載することが可能だ。
補給艦の艦内には、任務に必要な航空燃料や弾薬、食料、真水など、多種多様な物資を積載できるスペースが設けられている。
全長221メートル、基準排水量1万3500トンという巨体を持つ「ましゅう」型は、従来のディーゼルエンジンに代わり、ガスタービンエンジンを採用しており、これは補給艦にとって初の試みである。
ガスタービンエンジンの導入により、始動から離岸までの時間が半減し、運用能力が大幅に向上している。
また、最大速力24ノットを誇るこのエンジンは、高速を要求される護衛艦と並行しながら洋上補給を行うために特化されているため、その速さは任務遂行上、極めて重要な要素となっている。

さらに、艦内は医療設備も充実しており、集中治療室や45台のベッドを備えた病室が設置されている。
これにより、災害派遣や平和維持活動 (PKO) 在外邦人輸送といった多岐にわたる活動にも対応が可能である。

長期的な海外派遣活動にも耐えうるよう、航続距離の延伸が図られている点も、その多機能性を示している。
過去には、テロ対策特措法により、インド洋において断続的な補給活動を実施した。
具体的には、海上での阻止活動を展開する各国の艦艇に対し、継続的に補給艦を派遣し、必要な物資の補給を行ったのだ。
この支援がなければ、これらの艦艇は活動を数日で打ち切らざるを得ず、戦略的な拠点への再補給のために一時的に作戦区域を離れなくてはならない。
この一時的な離脱が作戦の効率を大幅に低下させることになる

なぜなら、艦艇が頻繁に作戦海域を離れることは、テロリストたちにとって他国への逃亡を容易にし、武器や麻薬などの国際テロの資金源を世界へと拡散させるリスクを高めるからである。
この連携と支援の継続は、国際的な平和と安全保障のために極めて重要な役割を担っていた。
そして防衛省は2024年度 新型補給艦1隻の建造費として825億円を計上している。
この新型補給艦は、約20年ぶりに新造されるもので、14,500トン型として計画されており、艦歴36年を数える「とわだ」の代替艦として整備される。
新型は、車両の積載・運搬機能を持ち、サイドランプが装備された設計を採用している。

この設計により、トラックなどに搭載されたコンテナをそのまま艦内に積み込むことが可能となり、物資の搬入・搬出がより効率的に行えるようになる。
これにより、艦内の貨物移送装置の自動化など、省人化も進められている。
就役予定は令和10年度中である。
一方、航空自衛隊においても、飛行中に給油を行う空中給油がある。
空中給油の神ワザ技術!ブームオペレーターの役割とは?
戦闘機などの軍用機は比較的搭載燃料が少なく、長時間の飛行が困難だ。
しかし、空中給油が可能になれば、基地に戻ることなく長時間の任務継続が可能となる。
これにより、戦闘機は任務の幅を広げ、より遠く、より長く飛ぶことができるようになる。
空中給油のもう1つの目的として戦闘機がミサイルなどの兵器を満載にした場合、エンジンパワーの関係から、その分燃料を減らさなければ離陸できない最大離陸重量という制限がある。
しかし、空中給油を行うことで、兵器と燃料のどちらも100%の状態で任務に向かうことができるというメリットもある。
空中給油の技術は、1921年11月2日に行われた歴史的な試みに遡る。

このとき、スタントマンのウェスリー・メイが複葉機間で、約19リットルのガソリンを背負って翼から翼へと移動し、給油を行った。
これが人類初の空中給油とされている。

航空自衛隊では、KC-767、KC-130H、そして新型のKC-46Aという3機種の空中給油輸送機を運用している。
これらは、航空燃料 (Kerosene) の「K」と輸送機 (Cargo Plane) を意味する「C」から「KC」という呼称が付けられている。
特にKC-767は、民間旅客機であるボーイング767をベースに空中給油機能が追加された機体で、航空自衛隊が4機、イタリア空軍が4機を保有しており、全世界でたった8機しか存在しない貴重な存在である。

空中給油の技術においては、KC-767が採用しているのは「フライングブーム方式」である。
この方式では、給油機が1本の給油管を伸ばし、受給機がこれに接続することで短時間に大量の燃料を補給できる。

対照的に、「プローブアンドドローグ方式」では複数のホースを使い、同時に複数機に給油が可能だが、フライングブーム方式の方がより高度な技術を要するため、操作には細かい調整と高い技量が求められる。
空中給油を行う際は、戦闘機がKC-767の左側に編隊を組んで待機し、1機ずつ給油位置に進入する。
給油位置は、KC-767からの指示灯に従い、適切な位置に機体を移動させることが要求される。
もちろんこの給油作業は、戦闘エリアから離れた安全な空域で行われる。
空中給油は精密な操作と高度な技術が要求される作業であり、ブームオペレーターの役割が極めて重要である。

KC-767での給油時、ブームオペレーターは機体底部に取り付けられた3次元立体視覚カメラを使用し、戦闘機の立体映像を基にして給油ブームの位置を調整する。
これにより、時速約700キロメートルで飛行中の両機の間隔を約15メートルに保ちながら、給油作業を行うことが可能となる。
ブームオペレーターは、給油ブームの先端にある「ラダベータ」と呼ばれる2枚の動翼をジョイスティックで操作し、これによりブームの位置を微調整できる。
この精密な制御により、機体底部の5台のカメラで給油口から伸びる約6メートルのパイプの位置を確認しながら、慎重に接続を行う。
給油が行える正確な位置に戦闘機が来ると、ブームの先端からノズルが伸び、受油機が操作して開けた給油口に差し込まれ、ノズルがロックされた後、燃料の供給が開始される。
KC-767は一回の給油で複数の戦闘機に燃料を補給することが可能で、給油作業にかかる時間は1機あたり約5分と非常に短い。
これにより、訓練時などでは一度に4、5機の戦闘機に順番に燃料を供給することができる。
給油が完了した受油機はKC-767の右側に退き、次の戦闘機が左側から進入し、迅速に次の給油が行われるシステムである。
また、KC-767は30トンの燃料を搭載した状態で約7200kmの飛行が可能であり、戦闘機約8機分の給油が一度の飛行で行える能力を持っている。
フライングブーム方式の利点は、短時間で大量の燃料を供給できることであり、戦闘機側のパイロットは給油機の操作によって燃料補給が完了するため、操作負担が軽減される。
ただし、空中給油の難易度は受油機の機種によって異なる給油口の位置や、天候、パイロットの技量や経験によって左右される。

例えば、F-15は左翼、F-2とF-35はキャノピーの背後に給油口があり、これらを調整するためには、ブームオペレーターの熟練度が求められる。


空中給油機であるKC-767は、一般的な旅客機とは異なり、その内装が非常に柔軟に設計されている。
この機体では、座席が固定されているのではなく、全てパレットに載せられており、床面には貨物を積載するためのレールが走っている。
パレットを前後左右に自由に動かすことができるため、内装の再配置が比較的容易に行える。
そのため、機内レイアウトは「貨物用」「人員輸送用」「貨客混載」といった複数のパターンに迅速に変更することが可能である。
ウクライナへの支援物資輸送の際には「貨物用」にして、防弾チョッキやヘルメットなどの装備品が積み込まれていた。
このように空中給油機は、給油以外の任務でも活躍しているのである。
次の動画では、世界初の無人給油機MQ-25の驚きの性能について解説しよう。
Amazonのオーディオブック12万タイトルの本を好きなだけお楽しみいただけます。・本の1冊分の月額で聴き放題
・料金をメリットが上回る
・いつでも読書できる
・読書量が格段に増え、積読が解消される
・長時間の読書も目が疲れない
・聴くたびに学びを感じる